【report】県北BCPアイデアソン#4 中間発表|イベントレポート

10/18(土)に開催した『県北BCPアイデアソン#4 中間発表』の様子を紹介します!
Business Challenge Program(県北BCP)では、新規事業開発を目指したアイデアソンを開催しています。このアイデアソンにて、参加企業であるリーダーの事業開発に関するアイデアを出し合い、参加者であるチャレンジャーとともにみんなで事業開発にチャレンジしていきます!
#4では、#3までのアイデア出しの成果と#6の最終報告会に向けたビジョンを発表。どのチームも中間発表に向けて準備を重ねてきました。当日は、3名のコメンテーターの方々やチャレンジャーの皆さんからコメントをもらい、発表後はチームで振り返りを行いました。#6の最終報告会に向けて、各チームのさらなる飛躍が期待できる中間発表となりました。
さてここからは、今回参加できなかった方々や当日の様子を振り返りたいという方々に向けて、中間発表の様子を紹介いたします!












まずは3名のコメンテーターを紹介します!
🙋♂️ 小野 哲人さん(株式会社小野写真館 代表取締役)

🙋♂️ 平岡 晃さん(株式会社HiOLI 代表取締役社長)

🙋♀️ 幡谷 佐智子(茨城県政策企画部県北振興局長)

今回は中間発表!
これまでの取り組みや現状の課題を8分間に凝縮してプレゼンテーションを行いました。どのチームの発表も完成度が高く、会場の皆さんにそれぞれの想いがしっかりと届いていました。このレポートでは、各チームの発表の要点をピックアップしてご紹介します。
📱 チームジンボウTech

私たちジンボウTech は、地域の「困りごとを抱える人」と「その困りごとを解決できるスキルを持つ人」をアプリでつなぎ、地域のさまざまな課題を解決していくサービスを開発しています。当初はデリバリーサービスとして構想していましたが、インボイス制度や営業コストの影響により方向転換し「人材不足を補い、地域内で助け合いを促すワーカーアプリ」として再設計しました。アプリの名称は「アプリでいくよ」です。
アイデアソン期間中には以下のことに取り組みました。
#1:壁打ちで課題を整理しました
#2:サービスの方向性を「地域の顔見知りネットワークを活かす」と定めました
#3:チラシを作成し、ターゲット層への訴求方法を検討・改善しました
現在は、市営住宅・県営住宅でのポスティングを通じ、スモールモデル地域での実証を進める準備を行っています。
課題は「アプリの利用者拡大」と「地域ネットワーク形成」の両立です。2025年度内に利用者500人・ワーカー20人・店舗20店の登録を目標としていますが、知名度向上・登録促進のための効果的な広め方に悩んでいます。アプリを広めるためのご意見やフィードバックをいただければと思います。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん)競合との差別化が “顔見知りのつながり” という点は非常に良いです。生活圏内で担当者の顔が見える仕組みは安心感につながると思います。地域に根ざした強みとして磨いていってください!
小野さん)「頼れる人がすぐそばにいる社会をつくる」というビジョンがとても素敵です。地方にこそ必要なサービスだと思います。運営面ではアプリ更新などの難しさがありますが、地域を絞ってお店を地道に増やすことが最大の強みになります。関わる人を集めてしっかり実行していけば、結果も出るのではないかと思いました。
幡谷)高齢者層にも届く仕組みづくりが鍵だと思います。ユーザーの声を取り入れつつも、誰に向けたサービスなのかを明確にしながら、地域の人が安心して頼れるプラットフォームを目指してほしいと思います。
🎁 チームゆかぴょん

私たちチームゆかぴょんは「オンライン販売をきっかけに始まる、県北6市町宇宙ファン化プロジェクト〜巻き起こせゆかぴょんエフェクト〜」として活動しています。オンラインショップを通じて、地域の生産者と全国のファンをつなぎ、地域の魅力ある商品を発信していくことを目指しています。
代表のゆかぴょんは、もともと大阪でクッション型トランポリンのオンライン販売を行っており、ECを通じて全国の子どもたちに商品を届けてきました。その経験から「オンライン販売で地域の良いものを広げたい」と考え、常陸太田市へ移住後にこのプロジェクトを立ち上げました。
当初は地域の生産者を訪ね、商品を一緒に販売する構想を立てていましたが、新規取引のハードルが高く、すぐには仕入れが難しいという現実に直面しました。そこで、自身の軸である「健康を応援する」というテーマに立ち返り、地域の素材と掛け合わせて新しい商品をつくる方向へ舵を切りました。その結果、大豆を使った商品、特に大豆ミートを販売することに決めました。チームメンバーと共に商品企画を進め、加工先も確定しました。今後は原料調達を進め、12月の最終報告会までに試作品を完成させる予定です。
将来的には、健康と地域企業のコラボレーションを軸に、大豆製品をはじめさまざまな商品展開を行い、より広いコラボレーションの可能性も探っていきたいと考えています。まだ具体的な部分は詰めていく段階ですが、最終報告会までにビジョンや具体的な商品、ECサイトでの競合調査などを進めていきます。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん)大豆ミート市場は競合が多いですが、オーガニック素材や健康という切り口での差別化は有効だと思います。商品のストーリーや地域性を価格にどう転化できるかが鍵です。ふるさと納税などとの連携も相性が良いと思います。
小野さん)ECの経験を活かし、試行錯誤しながら前進している点が素晴らしいと思います。世界的トレンドである大豆市場に注目し、オーガニック路線で差別化を図る戦略は非常に良いと思います。スピード感をもって販売に結びつけてください!
幡谷さん)地域おこし協力隊として、既存の商品の販売ではなく新たに商品を生み出す挑戦が素晴らしいです。加工先も見つかっているとのことで、今後は茨城県産の素材を活かした展開にも期待しています。道の駅などの地元の販売との連携も楽しみです。
👑 チームHUNTERxKING

私たちHUNTER×KINGは、県北BCPを通じて「会社の本質」と「私たちが何のために存在するのか」を真剣に見つめ直しました。当初、明確なビジョンを持たずに参加していた私たちは、どれだけアイデアを出しても方向性が定まらず、何を目指しているのかわからない状態でした。
その中で気づいたのは「存在意義である会社としての “軸” が欠けていた」ということでした。そこで私たちは、新しい事業を考えるよりも先に「自分たちの存在理由」を明確にすることからスタートしました。
5年間野生動物の被害対策という命に関わる現場に日々向き合う中で感じたのは、人間が自然に対して持つ「感謝の欠如」です。自然に生かされているはずの人間が、都合の悪い存在を “排除する対象” として扱っている現状を変えたい。その想いを原点に、私たちは新しいビジョンにたどり着きました。
ビジョン:人と自然が互いに敬意を持って共に生きる地球を取り戻す
この理念を実現するために、私たちは「コーポレートナイツ・グローバル100(世界で最も持続可能な企業100)」に選ばれることを目標としています。名誉のためではなく「自然と経済を両立できる日本発のモデル企業」として、理念を “結果” で世界に証明するためです。「命を奪う仕事の中に、命をつなぐ仕組みをつくる」この矛盾に挑戦し、人間の意識を変える経済の仕組みを構築する。それがHUNTER×KINGの挑戦であり、人類全体の意識を取り戻すための挑戦です。
現在は、理念・ミッション・ビジョン・バリューを整理し、最終報告会に向けてロードマップと構造設計を進めています。最終報告会では「何者なのか」を発表します。
【コメンテーターによるフィードバック】
小野さん)ビジョンが重く深く、非常に力強いと感じました。グローバル100を掲げるスケールの大きさも魅力的です。命に関わる事業はAI時代にも失われない分野です。高い売上目標を堂々と掲げ、理念と成果を両立させてください!
平岡さん)命と日々向き合う皆さんの仕事に尊敬の念を抱きました。理念を形にするには仲間づくりが鍵です。現在の社員全員が現場を理解し、ビジョンを共有しており、高い結束力を感じました。最終報告会での展開に期待しています。
幡谷)熊の被害などへの社会的関心が高まる中「感謝の欠如への違和感」という原点をビジョンに昇華させたこと自体が県北BCPの大きな成果だと思います。グローバル100を見据え、理念をぶらさずに進めていってください!
🤝 チームGood Last Life

私たちふれあい坂下は、日立市で20年以上にわたり地域の高齢者を支える「在宅支援型のノンプロフィット企業」として活動しています。20年ほど前の介護保険制度がなかった時代から、行政や福祉事業者が対応できない「要介護認定前のサービス」を担ってきました。
しかし近年、介護サービスの拡充により、ふれあい坂下の活動範囲は相対的に縮小しています。地域福祉の専門家からも「このままでは、ふれあい坂下に未来はない」と指摘を受けました。この言葉をきっかけに、私たちは “地域の便利屋さん” ではなく “地域に根ざしたノンプロフィット企業” としての立ち位置を再定義する決意を固めました。
県北BCPでは、これまで避けてきた「孤立無縁の高齢者支援」や「行政支援が届かない世帯への寄り添い」という課題に正面から向き合い、新たな事業「在宅セーフティネット」を立ち上げました。この事業では、行政や福祉団体もまだ十分に取り組めていない「人生の最後までよりそう」をキーワードに、安否確認を軸とした見守り支援を行います。利用者と「安否確認契約」を結び、定期的に見守りを行う仕組みをつくります。①お弁当配達での安否確認 ②訪問 ③高齢者を遠隔で見守る「ケアびー」の3つのサービスから現状に合ったものを選んでいただきます。
さらに、地域住民・行政・福祉事業者・地域コミュニティが集まり「人生100年時代をどう生きるか」というテーマの座談会を北部・中部・南部の3地区で開催し、最後に集大成として、専門家による全地域対象の講演会を開催する「転ばぬ先の杖事業」を実施予定です。この活動を通して、孤立の深刻化を防ぐ地域の共助ネットワークの大切さを、多くの住民と共に広く認識共有し、さらに「在宅セフティネット事業」を強化していきます。同時に、スタッフ不足・広報不足・資金不足といった課題の解消にもつながると期待しています。
また、ふれあい坂下そのものや「ふれあい坂下で働く人=正社員でありながらボランティア精神で働く人の集団」であることを知ってもらうために、クイズ形式の啓発ツールや、一目で理解できるチラシも作成しました。今後は企業ともWin-Winの関係を築き、介護離職防止に向けた講演会の受注など、新たな展開も模索しています。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん)「人生100年時代をどのように生きていくか」というテーマの座談会を通して地域住民に自然に関心を持ってもらう工夫が素晴らしいです。発信力を高めることで、認知を広げていけると思います。
小野さん)今後確実に日本社会に必要とされるサービスだと感じました。安否確認に特化する戦略が非常に合理的で、社会的意義も大きいと感じました。クイズ形式の広報も親しみやすく、多世代を巻き込む視点が素晴らしいです。
幡谷)行政が手の届かない “共助の領域” を支える重要な取り組み。ふれあい坂下さんの活動は、行政・民間・地域をつなぐハブとして大きな役割を担ってくださっています。今後も理念をぶらさず、構造的な連携を進めてほしいです。
🌳 チームELM Resort

Elm on the Beachは北茨城市の海沿いに位置するリゾート施設として、地域と世界をつなぐ新しい交流拠点づくりに挑戦しています。
代表のクリスさんは、東京での多彩なキャリア(都内の有名クラブ勤務、有名人の運転手、インターナショナルスクールの先生や幼稚園の運営、モデル活動など)を経て、1年前に茨城県へ移住しました。これまでの経験とネットワークを活かし、国道6号線沿いにElm on the Beachをオープンしました。
施設は太平洋を望む絶好のロケーションにあり、キャンプ・海遊び・宿泊などを楽しめる空間として、国内外から注目を集めています。オープン以降、テレビ出演やSNSを通じて話題となり、1ヶ月に約50組の外国人観光客が訪れるようになりました。朝食では各国の食文化に合わせたメニューを提供し、来訪者が楽しめるように工夫しています。
今後の中長期計画としては、クラウドファンディングを実施し、地元金融機関との連携も強化して、施設のリゾート化や活動の拡大に必要な資金を確保していきたいと考えています。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん)「地域にみんなが集まって話せるハブのような場をつくりたい」という構想がとても魅力的です。海外からのボランティアやメディアが自然と集まるのは、クリスさんの国際的ネットワークと発信力の賜物だと思います。今後の展開に期待しています。
小野さん)北茨城市はインバウンド観光地として大きな可能性を秘めています。リゾートビル構想のように “食・文化・交流” を一体で体験できるまちづくりは、地方が抱える課題や日本全体の社会課題の解決にもつながると思います。クラウドファンディングによる拡張にも大いに期待しています。
幡谷)家族やボランティアと一歩ずつ形にしている姿勢が素晴らしいです。コミュニティスペースを起点に、イベントや海辺のアクティビティなど、地域と観光を結ぶ取り組みがどんどん広がっていくと思います。“暮らすように旅する” 体験を提供する場としてのニーズの高まりもあります。今後が楽しみです。
💄 チームB&be

私たちB&beは「日立市を日本一美容が学べる町にする」をビジョンに掲げ、美容を通じて地域の活力を高めるプロジェクトに取り組んでいます。私の36年の技術、資格、そしてこれまでの人脈を活かして、人の人生に変化のきっかけを提供できると確信しています。私は、美容資格取得支援スクール「コスメライセンススクール茨城校」と「N’sビューティスタジオ」を運営しています。
美容業界では、資格を取得してもその後の活かし方がわからない方が多く、集客や法令知識などを学ぶ機会も限られています。そこでB&beでは「人・資格・お金」が循環する仕組みを構築し、資格取得者が自立して働き続けられる環境づくりを進めています。テーマは「資格を活用して人を輝かせ、未来をつくる」です。具体的な目標は、月に50〜100人の資格取得者を育成することです。高校生・大学生から子育て世代、セカンドキャリアまで幅広い世代を対象に、美容を通じたキャリア支援を行っています。例えば、北海道の高校では男子学生にスキンケアとビジネスマナーを教えています。日立市内の高校では、美容とコスメの講座を行っています。その他、子育て世代の資格取得支援、50代・60代のセカンドキャリア支援など、多様な層へのサポートを展開中です。
事業計画は3段階で構成しています。
ステップ1:美の拠点として駅前から展開開始
ステップ2:資格取得者と連携し、創業支援を行う
ステップ3:駅前に資格取得合宿施設を建設
講師育成も重要な柱であり、2026年に向けて講師募集を開始予定です。各協会や美フェスなどとの連携を強化し、オンライン・対面講座を通じて美容資格を広く普及させていきます。入口となる講座では、大学生向けに1,000円の講座を開催し、講師の時給10,000円を目指すなど、実践的な収益モデルも構築しています。
出張講座、オンライン・対面講座、自治体連携により「人・資格・お金」が循環する仕組みをつくります。この仕組みにより、美容業界の最大の課題である「受講生獲得」を解決できます。一般顧客からの新たな受講生獲得につながり、単独ではできないことをチームで循環させる仕組みとなります。
【コメンテーターによるフィードバック】
小野さん)日本化粧品検定を他の取り組みと組み合わせると非常に強いと思います。そして、大畑さんはそのトータルプロデュースを経験と自信を持ってできるので、まさにオンリーワンの存在だと感じました。女性が一生涯、外で稼げる仕事で、全国どこに行っても通用する技術を身につけられるというのは素晴らしいです。全国に広がるチャンスがあると思います。
平岡さん)日立市を中心にまず活動されると思いますが、毎月50~100人の資格取得者が増えると、日立市の美容人口がかなり増えると思います。今後は、日立市から茨城県外へもこの人材やノウハウを広げていく展開も進めていただけると、より大きな可能性があるのではないかと感じました。
幡谷)日立市を「日本一美容が学べる町にする」というビジョンは、新しい日立のイメージづくりや地域活性化、美容業界の未来を見据えた明確なテーマで、とても期待がもてます。日立市との連携や創業支援なども含まれているとのことで、ぜひプランの実現に向けて頑張っていただければと思います。
🍚 チームにこにこはっちぃ〜

私たちにこにこ地域食堂は「みんなでつくる、みんなの “実家”」をコンセプトに、誰もが安心して帰ってこられる “心のよりどころ” を目指しています。活動拠点は高萩市で、開催場所は私の経営する簡易宿舎Luana、調理は祖母の営む焼肉寿苑に協力してもらっています。子どもからシニアまで幅広い世代が参加できる地域食堂を月1回開催しています。平均参加者数は約40名、1周年記念では100名の方が参加してくださいました。
この活動の原点は、地域の優しさに支えられて育った私自身の経験です。「地域に育ててもらった恩を返したい」「誰かの力になりたい」という想いから、食事の提供だけではなく食育・教育・体験・交流を通して、地域全体が笑顔でつながる “ビッグファミリー” のような場所づくりを目指しています。
現在は市の助成金「高萩まちづくり支援金(10万円)」を主な運営資金としていますが、2026年度で終了予定のため、自主運営の仕組みづくりが急務となっています。そこで、県北BCPでは「サステナブルな事業にするための商品開発」をテーマに、寄付や助成金に頼らない資金循環の仕組みづくりに挑戦しています。その第一歩が、地域マルシェへの出店です。安全素材の「カスタムクレヨン」を使った体験型ワークショップを実施し、子どもたちが自分の色を選んで世界にひとつだけのクレヨンをつくります。楽しみながら表現力を育みます。この活動を通じて、地域との信頼関係を築き、地域食堂の想いも届けます。
収益モデルとしては、1日5時間来場者約400人規模のイベントで、食堂1回分の開催費用の7割をまかなう計画です。楽しみながら運営を支える仕組みづくりが、サステナブルな活動への第一歩です。さらに「こどものまち」の仕組みづくりなど、地域の子どもたちが社会体験できる新しい仕組みも準備中です。
2026年はイベントでの資金調達、2029年にはキッチンカーによる移動式地域食堂、2034年にはフリースクールをメインとした事業形態に変えていく計画です。私の最終的な理想は、「地域食堂がなくてもいい社会」です。孤立や貧困がなく、地域の中で自然と支え合う社会。その理想に向けて、今は小さな仕組みづくりから挑戦しています。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん)「地域食堂がなくてもいい社会」というビジョンが印象的です。収益化に向けたカスタムクレヨンのアイデアも素晴らしいです。子ども向けだけではなく、大人の時間を活かす仕組みも考えると、さらに広がりが生まれると思います。
小野さん)「みんなでつくる、みんなの “実家”」という言語化が素敵だなと思いました。想いの本質が伝わってきました。本当に大事だと感じたのは、夢を叶える上で、以前はお金に対して少し抵抗やブロックがあったとしても、世の中を良くするためには継続性が重要だという視点に気づかれたことです。これは非常に大切な視点だと思います。
幡谷)地域食堂を継続可能な形にするという目的に対し、収益構造を見いだせたことが大きな成果だと思います。カスタムクレヨンは収益の柱になると感じました。今後は計画を具体化し、発展性も見据えながら、さまざまなアイデアを取り入れていってください!
🔈チーム赤津ねじ商店

私たちチーム赤津ねじ商店は「ネジをお土産にする」という挑戦を通じて、ものづくりのまち日立の誇りを形にするプロジェクトに取り組んでいます。現在の課題は2点です。
① “日立らしさ” をどのようにお土産に落とし込むか
② 一般の方にネジを “面白い” と感じてもらえるか
きっかけは、赤津工業所の赤津社長の「日立らしい “形に残る” お土産をつくりたい」という想いでした。ものづくりのまち日立には、実は “ものづくりのお土産” がありません。だからこそ、赤津工業所の技術と、日立の誇りを掛け合わせた “唯一無二のお土産” をつくりたい。これがこのプロジェクトの原点です。
はじめはネジ型グミを検討しましたが、国内で3D立体グミをつくる設備がなく断念しました。方針を転換し、まずは小さく、自社の工場でできることから始めました。本物のネジを使ったアクセサリーやキーホルダーの試作からスタートしました。中学生の職業体験でも製作に取り組み、ものづくりの面白さを共有しています。
9月のアイデアソンでは試作品アンケートを実施し、最も支持が高かったのはキーホルダーで、価格帯は500〜999円であれば買いたいという声が多く、手応えを得ることができました。「赤津の刻印やプレートを入れてほしい」「集めてつなげられる仕掛けがほしい」などの具体的な声も寄せられ、改良の方向性が明確になりました。
次の一手として、ガチャガチャの展開に注目しています。理由は「設置スペースが小さい」「電源不要で運用しやすい」「コレクション欲と相性が良い」という3点です。まずは本社で運用し、将来的には駅や観光案内所へ拡大する計画です。雑貨・食品等への横展開も視野に入れています。私たちは、ネジを「人と人 / 人とモノをつなぐ象徴」と捉え “愛着の持てるネジ” を目指します。
この活動を “日立らしいお土産” に育てるためには、どんな要素が必要だと思いますか?そして、一般の人にネジを「面白い」と感じてもらうには、どうすればいいでしょうか?ぜひ皆さんのフィードバックをお聞かせください。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん) “日立らしさ” の定義をチームで言語化すると、企画やデザインの一貫性が高まると思います。「どうすれば一般の人に面白いと思ってもらえるか」については、体験が最短です。工場見学→お土産購入の導線がつくれると、収益化の角度も高くなるのではないでしょうか?
小野さん)「ネジは500年以上、人類の進歩を支えてきた」という言葉が刺さりました。ガチャガチャは小面積・電源不要で伸びしろも大きいです。「日立らしさ」についてですが、最終的には “売れたものがその土地らしさ” になります。赤津ねじ商店さんがネジを売りまくって「日立といえばネジ!」というブランドをつくっていけると思います。
幡谷)100年を超える製造技術というコアなリソースを活かして観光土産という新しい分野にチャレンジされているのは、とてもユニークで地域活性化にもつながる素晴らしいアイデアだと思いました。「日立らしさ」の表現についてですが、集めたネジをコンプリートすると、日立のモチーフになるような仕掛けがあっても面白そうです。例えば、全部集めると「日立の大煙突」や「桜」など、日立を象徴する形になる──そんな遊び心があると、より “日立らしさ” が伝わるのではないでしょうか。
🎬 チームタンポポ

2024年4月より茨城県北地域おこし協力隊【起業・複業型】(KENPOKU PROJECT E)として、日立市にて活動しています。私のことは “ブランディングする人” だと思ってください。直近は企業広報のキャリアですが、10代からギャルサーを作りイベント運営もしていました。
そんな私は「ギャルマインドで人とコトとモノをつなぐ」を軸に活動しています。
着任からの半年間で、行政関連案件を6件担当させていただいております。内容はセミナー講師やイベントの映えスポット作成、イベント企画です。
日立市を選んだ理由は、ポテンシャルが高いからです。
一方で課題は20〜30代女性の人口減少です。人口流失の原因には仕事がないことも理由の一つにあります。
そんな学生や女性がこのまちで挑戦できる舞台をつくることを目標にしています。
現在の私のチームには、学生サークルのメンバーや、SNSマーケター、ライターなど多様なメンバーがいます。私たちは以下の4つの軸で取り組んでいます。
①地域活性化事業
②PR・ブランディング
③キャリア支援
④コミュニティ / メディア運営
現在は2つのプロジェクトを推進中です。
常陸マルシェ:その土地の価値を上げる “屋内型マルシェ” です。会場は商業施設ヒタチエを想定しています。茨城県立大子清流高等学校 農林科学科 森林科学コースの生徒さんに地域資源活用の一環で制作マルシェ用テーブルの製作を一部していただいております。
運営には大学生を中心に若い世代を起用します。ポップアップのような洗練された空間を演出し「このマルシェに出るとカッコイイ」と感じてもらえるブランドを目指します。全国の企業・自治体とも連携予定です。
常陸暮らし:地域の生産者のストーリーを記事・動画で発信するオウンドメディアです。ファンを育て、将来的には購買やイベントにつなげていく仕組みを考えています。
これらの二つを軸に、地域ブランディングのプロフェッショナル集団(クリエイティブファーム)を育てます。
Web / SNS / ディスプレイ(映えスポット)までトータルで設計する「提案デザイン」の考え方で、まちおこしに特化したマルチプレイヤー集団をつくります。
事業計画は5年で年商8,000万円、3年目からは地域型クラウドファンディング事業の自社展開を見据えています。
私は企画もPRも現場もライティングもできる “ハイブリッドプレイヤー” です。今後は、私と同じように地域で活躍できるマルチプレイヤーを育て「常陸マルシェ」と「常陸暮らし」からカルチャーを生み出していきたいと思っています。
【コメンテーターによるフィードバック】
平岡さん)外からの視点で “まだ気づかれていない魅力” を発信する価値が大きいと感じます。着任から半年間で6案件の獲得は見事です。複数柱の優先度は、まず「常陸暮らし」の継続発信と受託案件の成果、次に来春のマルシェ準備という整理も納得できます。
小野さん)県北地域初のクリエイティブファーム構想は挑戦的で面白い取り組みです。「リアルなマルシェにわざわざ行く理由づくり」にも、猪野さんがこれまで培ってきたブランディングの経験がしっかり生かされるのだと思います。マルチにできる強みは大きいですが、自分が動かなくても回る仕組みづくりが成長の分岐点だと思います。分岐点の先にクリエイティブファームとしての姿がきっと見えてくるはずです。
幡谷)エネルギッシュな推進力に加え、プロフェッショナル集団をつくるための人材育成が重要だと思います。大学との連携で若者が地域で実践する場が生まれていて、素晴らしいです。これからも色々な方を巻き込み活動を広げていってください!
今回のフード・ドリンクは…

株式会社ただいま COFFEE STAND GENKANより、神定祐亮さんが出張サーブ!さらに、菓匠宮川が県北BCPに初登場し「焼きドーナツ・絆の和」をご提供くださいました。プレゼンの合間や休憩時間には、美味しいフードとドリンクで頭も心もリフレッシュ。緊張感に包まれたプレゼンの合間に、ほっとひと息つける優しい時間となりました。
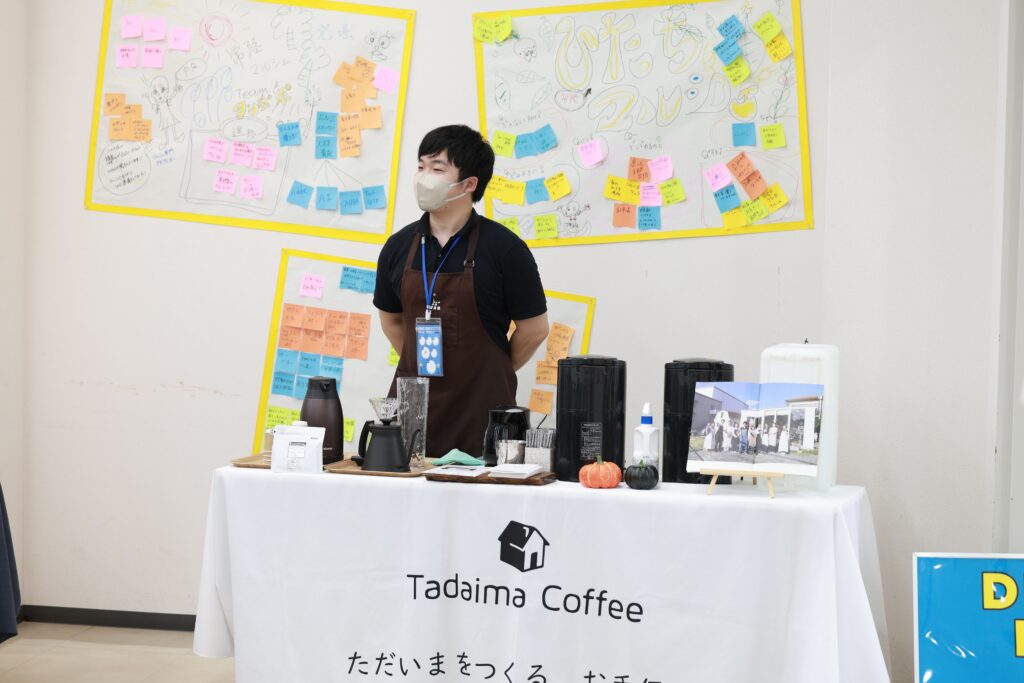

今回もまちのこ団のあそび場をお届け🧸
あそび場と会場を行き来したり子どもの声が会場に聞こえたり…!大人もこどもも全力で「今、この瞬間」を過ごしていました!


最後に#5以降に向けて中間発表の振り返り!
どのチームも事業を前進させるために真剣に取り組んでいます。コメンテーターのところに質問に行くチームの姿もありました。






県北BCPアイデアソン2025、最終報告会まであと1ヶ月🔥

県北BCPアイデアソンは、12月までの合計6回実施します。
これまで参加できなかった方や「ちょっと覗いてみたい」「どんなイベントか気になる」という動機でもOK!ご都合の合う日程にぜひご参加ください!
📅 今後の開催予定
・11/15(土) 13:00〜18:00 アイデアソン# 5
▶︎ メンター:合同会社モテアソブ三軒茶屋 高野一樹さん
・12/20(土) 13:00〜18:00 アイデアソン #6
▶︎ 最終報告会












